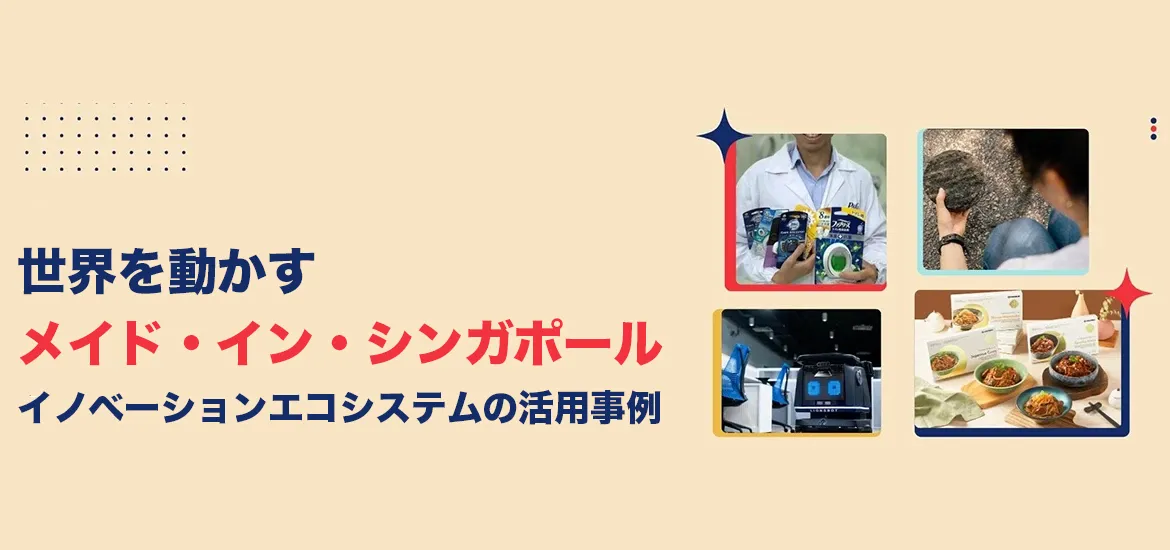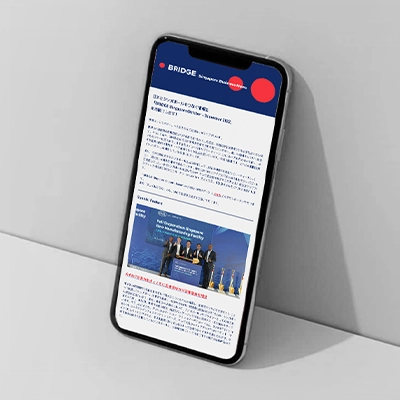当記事では、グリーンテック、消費者向け製品、食品、ロボットなど、まったく異なる分野のものでありながら同様に強いインパクトを持ち、シンガポールの多業種に渡るイノベーション・エコシステムの奥深さを示す4つの製品に焦点を当て、紹介する。
ビジネス成長のためのイノベーションやシンガポールの研究開発エコシステムについての詳細はこちら
1. 未来の味わい:キッコーマンによる植物由来のヌードルキット「Harumaru」

しょうゆで広く知られるキッコーマンは、代替タンパク質食品の分野においても新たな展開を見せている。それが、シンガポールで開発・試験販売された植物由来のヌードルキット「Harumaru」だ。
Harumaruは日本的な味わいを取り入れつつ現地の味覚に合う、手軽に楽しめる植物由来のメニューとして企画された。ひよこ豆と小麦からつくられた麺に和風の植物由来ソースを合わせ、多忙な消費者が数分で作れる植物由来の食事を実現した。
多様な人口構成と、食品分野における充実したR&D基盤を有するシンガポールは、Harumaruの立ち上げにとって最適な環境となった。
キッコーマンのR&D拠点は、2005年にシンガポール国立大学(NUS)内に設立され、その後、シンガポールが誇るバイオメディカルR&D拠点であるバイオポリスに移転した。 当地にて同社は、科学技術研究庁(A*STAR)やEDBをはじめとするシンガポールの官民連携によるイノベーションネットワークを活用し、食品科学における取り組みを拡大、革新的な食品のテストを行っている。
「R&Dから商業化にいたるまで、イノベーションプロセスを加速させる上で EDBの手厚い支援には、大いに助けられました。 シンガポールは企業にとりイノベーションの価値あるモデルを提供してくれています。」
キッコーマン
取締役常務執行役員
松山 旭博士
Harumaruは、キッコーマンにとって急速な成長を見せている植物由来のインスタント食品市場への新たな挑戦であり、シンガポールのビジネスフレンドリーな環境、明確な規制、様々な分野にまたがるパートナーシップを体現するものでもある。こうした強みによりグローバル企業は、事業を広い地域へ拡大させる前に、シンガポールにて先行的に新たなアイデアを試行・改良することが可能となる。

2. 進化したスマート清掃ロボット:LionsBot社「R3 Vac」&「R3 Scrub Pro」

街や公共エリアが清潔で手入れが行き届いていることが世界的に知られるシンガポール。あるシンガポール企業が先進ロボット工学を活用し、その評価をさらに高めている。
シンガポール発のスタートアップ企業LionsBot社は、公共スペースや民間施設の床面を自動で清掃するロボット「R3 Vac」と「R3 Scrub Pro」を開発した。業務用モデルである「R3」シリーズには、高度なセンサー、経路最適化AI、直感的なユーザーインターフェースが実装され、これらの機能が効率性を向上、人的な監視の必要性を軽減させる。ロボットは周囲の環境を素早く学習して適応し、複雑なレイアウトでも正確かつ効率よく清掃作業を行うことができる。
LionsBotの成長と発展は、政府のイニシアティブであるNational Robotics Programme(NRP)が立ち上げたアクセラレータープログラムRoboNexusによって支えられている。RoboNexusはアクセラレーターとして将来有望なロボット関連中小企業と、学術界・産業界・公共セクターの専門家を連携させ、試作品開発から製品化までのスピードアップを支援している。
LionsBotはこれまで、ロボットの市場展開のため、資金提供、メンタープログラム、商品化サポートといった支援をRoboNexusから受けており、ローカルのエコシステムを活用し、シンガポールから30か国以上へと事業を拡大している。 同社はこれまでにインタークリーン・アムステルダム・イノベーション・アワード、欧州清掃衛生賞(European Cleaning and Hygiene Award)、シンガポール・グッド・デザイン・マークなどを受賞している。
3. フレッシュな空気のためのフレッシュなアイデア:P&Gシンガポールイノベーションセンター発のエアケア製品「ファブリーズ」&「アンビピュア」

プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)のシンガポールイノベーションセンター(SgIC)の研究チームにとって、革新的科学アプローチによる消臭剤の再開発は重要任務であった。
2014年の設立以来、SgICはシンガポール最大級の民間研究施設に成長し、アジア太平洋地域におけるP&Gの重要なイノベーション・ハブとしての役割を果たしており、半数以上をシンガポール人が占める500名近い研究者が在籍している。
この研究施設で生まれた代表的な製品に「ファブリーズ」や「アンビピュア」といったエアケア製品があり、「プロジェクト・マーライオン」というコードネームのもと、シンガポールの地で、次世代の製品のための初期顧客調査から、受動拡散を促進する独自の3Dパッケージング開発にいたるまでが行われた。
SgICによる革新的な技術開発は、ファブリーズとアンビピュアを北米、日本、英国のエアケア市場におけるトップブランドへと成長させた。
こうした開発の裏には、エアケア部門の技術研究開発リーダーであるシンガポール人科学者のDesmond Ng博士の存在がある。2019年のP&G入社以来、博士は抗菌香料の配合、膜分離技術、芳香制御装置に関する14件の特許を出願している。
「SgICでの仕事を通じて、実験室で行うことだけでなく、アイデアを形にし、 消費者の手に届けるには何が必要かを理解できるようになりました。 自分の仕事が世界中の何百万人もの消費者の暮らしに影響をもたらしていると 実感ができることに喜びを感じます」
Desmond Ng博士
エアケア部門技術研究開発リーダー
実感ができることに喜びを感じます」
P&Gの成功は、シンガポールが多国籍企業のR&D拠点として選ばれる理由 ―アイデアから市場展開までのイノベーションを支える強力な人材と地域的利便性をもつエコシステム ― を表している。
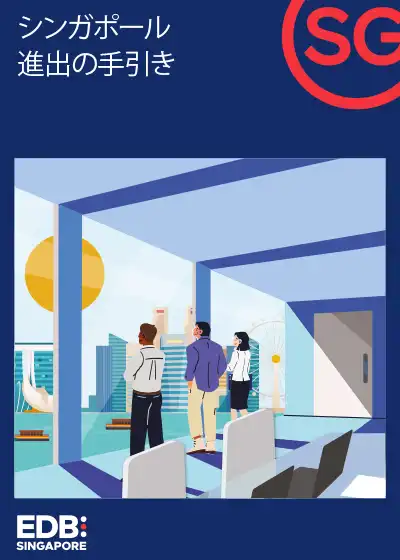
シンガポールにおける地域統括拠点や研究開発拠点の設立についてのガイドブックはこちら
4. 環境にやさしい道路整備の礎を築く:Magorium社「NEWBitumen」

シンガポールのスタートアップ企業Magorium社により、プラスチックごみに新たな命が吹き込まれ、道路舗装材へと生まれ変わっている。 何世紀もの間、道路の舗装にはアスファルトが使われてきた。これは石油由来の原料であり、製造過程において大量の二酸化炭素が排出される。MagoriumのCEOであるOh Chu Xian氏は、家業である道路建設業が行ってきた従来型のものとは異なる、環境にやさしい代替素材を生み出すことを考え、ゴミから道路を作り出す試みを始めた。
ディープテック企業である同社は、埋立処分されるごみの削減、そしてグローバルな気候変動対策への貢献を目指し、未分別で汚れたままのプラスチックごみを道路建設用資材に変える新たなテクノロジーを開発した。
同社の特許製品「NEWBitumen」は、従来のアスファルトと比べ、生産1トンあたり300kgの二酸化炭素排出が削減できると推計されている。同社は、トゥアスにある工場において「NEWBitumen」を用いた「エコロード」を初整備、それ以降、シンガポール各地で10以上のエコロードが敷設されている。
Magoriumはまた、循環経済を推進するために、他業種のパートナーとの連携も進めている。フランスの大手バイオ医薬品企業サノフィとの提携では、使用済みのインスリンペン型注入器を回収し「NEWBitumen」の資材として再利用している。これはシンガポールにおけるサノフィの最新製造施設の敷地内道路にも用いられた。
同社の道路建設ソリューションは、プラスチックごみや二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、広く事業展開できる持続可能なインフラのためのスケーラブル・モデルも提供する。Magoriumは東南アジア全域への展開を視野に入れ、プラスチックごみのより効果的な処理や、環境にやさしい道路整備技術の導入に関して、各国を支援することを目指している。
イノベーションが生まれる国:グローバル・テストベッドとしてのシンガポールの強み
ここで紹介したイノベーション事例は、それぞれが優れているのはもちろんだが、まとめて捉えれば、世界的な影響をもたらすアイデアの発信地としてのシンガポールに対する評価の高まりという大きな意味を持つ。
これらの成功事例に共通するのは、研究開発や試行から、パートナーシップや事業拡大にいたるまで、イノベーションのすべての段階を支えるよう設計されたエコシステムだ。
イノベーションは単独で生まれるものではなく、様々なセクターから協力者が集まり、人材が育まれ、アイデアが積極的に生み出される環境でこそ発展する。複雑な課題に対するソリューションとして創り出された「メイド・イン・シンガポール」の製品だけでなく、それを実現した人々やパートナーシップも賞賛に値すると言っても過言ではない。