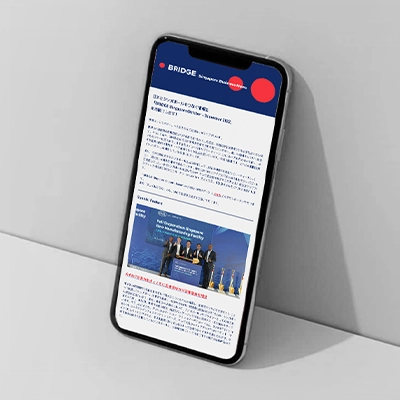持続可能性、自動化、技能研修強化
―三井化学は2050年までの温室効果ガスの排出量実質ゼロ(カーボンニュートラル)達成を目標にしています。この持続可能性目標に沿って、シンガポールの製造拠点をどのように変革されるのでしょうか。
淡輪:カーボンニュートラルの実現は、三井化学が環境との持続可能なバランスを保つための重要なステップです。そのためには世界中の製造工程のさまざまな部分での変革が必要です。
シンガポールでは、各製造プラントが業務最適化を通じて、水道光熱費などのユーティリティーや原材料消費量などの効率改善を継続的に行っています。また、他社と協力して、プラント内に太陽光パネルを設置し、日常的な電力使用を補完するための太陽光発電の活用にも取り組んでいます。製造工程では大量の電力を必要とするため、近い将来のプラントでのグリーン電力の使用を積極的に検討しています。
―シンガポール拠点での製造プロセス強化のため、自動化と新技術の導入についてお聞かせください。また、技術習得に向けて、従業員にどのような研修や支援プログラムを実施していますか。
淡輪:三井化学は、製造・業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を開始しました。これらの取り組みは、シンガポールの関係会社を含む世界中の各拠点に段階的に適用される予定です。
DXの推進支援では、従業員や管理職を対象とした一連のDX学習コンテンツを展開しました。従業員が新しい技術を習得する準備を整え、デジタルスキルの向上と新しいタスクを遂行する能力を向上させるために、ツールやリソースの提供を拡大しています。
―三井化学はシンガポールでローカル人材の雇用を積極的に推進しています。そのメリットは何でしょうか?また、これまでにどのようなプログラムを実施されてきましたか?
淡輪:三井化学は、新しい才能を生み出し続けるシンガポールの教育機関と、採用活動、ネットワーキング、奨学金、高等専門学校(ポリテクニック)とのインターン制度などで積極的に提携してきました。
「三井化学プロセステクノロジー(MCPT)奨学金」は、ポリテクニックと協力して、卒業後に入社する若い才能を探し出すための取り組みの一部です。
社内の学習と人材開発の枠組みは、スキルズフューチャーの「Skills Framework」に合わせて設計され、従業員の能力開発を最大化することを目指しています。2019年には、従業員技能向上に貢献した雇用主に贈られる「SkillsFuture Employer Awards」を受賞し、技能向上と生涯学習の促進を確約しています。
リーダーシップ開発の面では 、2010年代後半から指導者育成のため「三井化学能力開発プログラム」を導入しています。若手から中間管理職レベルまでの人材育成を行う、社内向けにカスタマイズされたリーダーシッププログラムです。