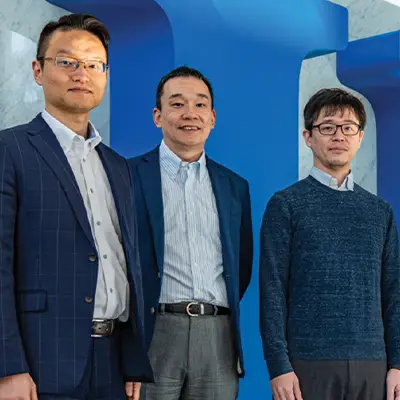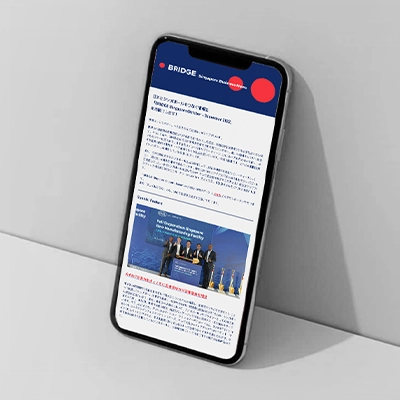Q:日本本社との連携について、特に製品開発やマーケティングの面でどのような協力体制を構築されていますか。
人材交流や日頃からの情報交換を通して、日本国内で培った販売、マーケティング、商品開発の知識を共有しております。シンガポール現地会社でASEAN各国の市場にマッチするようにローカライズし、各国のお客様に求められる商品やサービスを提供しております。
Q:東南アジア向けに開発・改良された製品はありますか。東南アジアと日本の消費者にはどのような違いがありますか?これらの違いを、製品開発にどのように反映させていますか。
A:現地の味覚に合わせたテリヤキソースや鍋つゆ、すき焼きのたれなど、幅広い商品を開発しています。東南アジアでは日本の消費者と比較して、一般的に甘みと濃厚なうま味のある味を好み、強い香りは好みません。しょうゆの風味と香りのバランスを保つことで、お客様の嗜好に応えています。
R&D施設の設立と拡張
Q:御社はシンガポールのR&D拠点を2005年にシンガポール国立大(NUS)内に設立し、その後バイオポリスに移転されました。この戦略的な判断の背景と、それによってもたらされた具体的なメリットについてお聞かせください。
A: KIKKOMAN SINGAPORE R&D LABORATORY PTE. LTD.(以下KSL)設立当初は、アジアの伝統的な食品や原料に焦点を当てた基礎研究と商品開発を主務としていました。2013年からは、KIKKOMAN MARKETING&PLANNING ASIA PTE.LTD.(以下KMPA)を設立し、東南アジア地区の商品開発を推進する一方、KSLはNUSやA*STARとの協働を積極的に進め、主に基礎研究からの成果創出を目指しています。バイオポリスへの移転により、A*STARとの連携が強化され、様々な研究機関や研究員同士の交流も活発となり、日常的な情報交換や共同研究の機会が自然と生まれることで、研究活動のさらなる深化と拡充が実現しています。
ローカル人材とエコシステムパートナー
Q:Harumaru Chickpea Noodle Kitの開発で、シンガポールの人材やサプライヤーエコシステムをどのように活用されましたか。 また、現地パートナーとの協業で得られた知見や課題についてお教えください。
A:Harumaru Chickpea Noodle Kitは、弊社が開発したプロトタイプを、シンガポールの製造業者との連携を通じて製品化した成果です。現地製造業者やマーケティングパートナーと連携して、テストマーケティングを実施したことで、お客様の行動や嗜好に対する理解が深まりました。これらの知見は今後の製品改良や戦略立案に活かしてまいります。
A*STARと研究開発コラボレーション
Q:キッコーマンとA*STARとの提携はどのように行われていますか。
A:A*STARとは、これまで酵素や有用物質の探索から始まり、さまざまな共同研究を実施してきました。近年では、代替タンパク質の開発や、ライフサイクルアセスメントに関する取り組みなど、研究領域を広げながら連携を深めています。
Q:A*STARやEDBとの協働を通じて得られた具体的な成果はどのようなものでしたか。
A:Harumaru Chickpea Noodle Kitのテストマーケティングは、パートナー探索を含め様々な面でEDBの支援を得て実現しました。また、A*STARの研究ネットワークを活用することで、研究活動の幅が広がりました。
Q:今後さらに期待されるコラボレーションや支援についてお聞かせください。A*STARとどのような提携が期待されますか。
松山:今後もA*STARとは、食品加工技術やバイオ関連分野における共同研究を継続的に進めていく予定です。特に、AIやバイオ先端技術へアクセスし、研究開発に応用することで、研究の質の向上や新たな価値創出につなげていきたいと考えています。こうした取り組みは、弊社の研究員にとっても貴重な学びの機会となり、人材育成の面でも大きな意義があると期待しています。